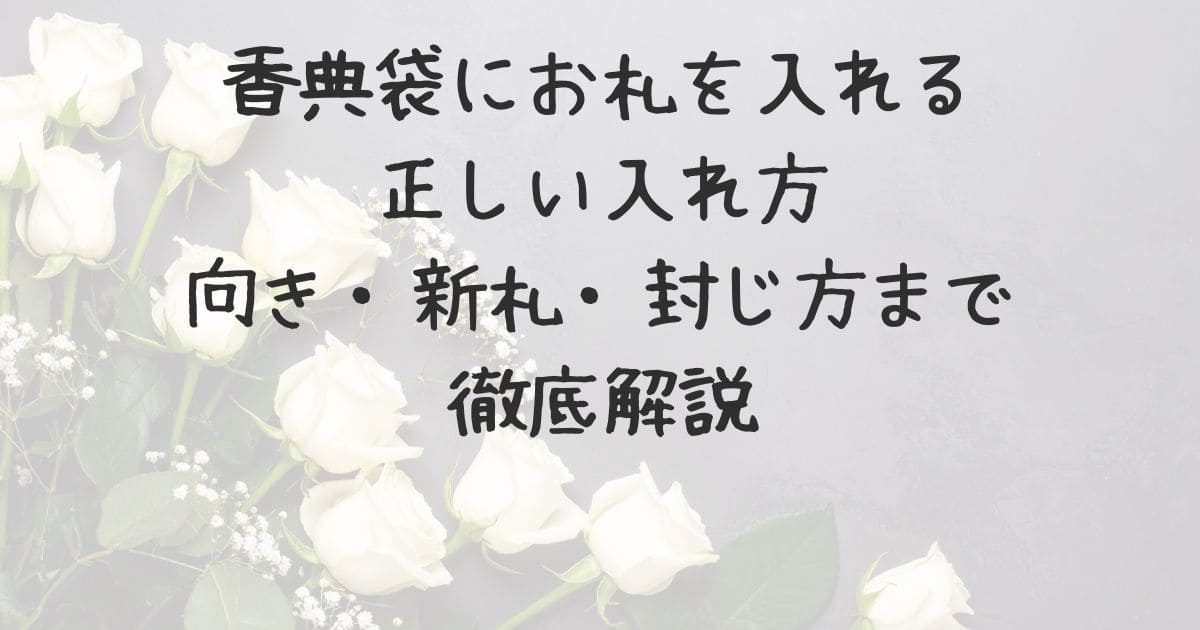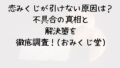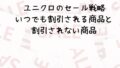葬儀に参列する際、最も気を使う場面のひとつが香典袋の準備です。
特に「お札の向きはどうするのか?」「新札は使っていいのか?」といった細かいマナーは、慣れていないと迷ってしまいますよね。
香典袋にお札を入れる方法を誤ると、遺族に対して失礼にあたるだけでなく、自分自身の常識も疑われてしまうことがあります。
この記事では、香典袋にお札を入れる正しい入れ方を、向きや新札の扱い方、中袋の有無、さらには封じ方や渡し方のマナーまで網羅的に解説します。
初めて葬儀に参列する方や、マナーに自信がない方でも安心できるよう、表や具体例を交えてわかりやすく整理しました。
この記事を読めば、香典袋のマナーをしっかり理解し、自信を持って故人への敬意を表すことができます。
香典袋にお札を入れる正しい基本ルール

香典袋にお札を入れる時には、ただ現金を包めば良いわけではありません。
実は細かなマナーがあり、それを知らないと失礼になってしまうこともあるのです。
まずは香典袋とお札の関係を理解し、基本のルールを押さえていきましょう。
香典袋とお札の関係を理解する
香典袋は、故人への弔意を現金という形で表すためのものです。
そのため、お札の扱い方ひとつにも「敬意をどう示すか」という意味が込められています。
お祝いごとのご祝儀袋と違い、香典袋では控えめで慎ましい扱いが基本です。
お札の向きや折り方も、そうした配慮を表す大切な要素です。
表面と裏面、お札の上下の見分け方
お札の表面は、人物の肖像が描かれている側を指します。
裏面は建物や風景が描かれている側で、上下を見分けるには肖像の向きに注目しましょう。
香典袋では、この表裏や上下の扱いに決まりがあり、誤るとマナー違反と受け取られる可能性もあります。
まずは下記の表で確認してみてください。
| 位置 | 特徴 |
|---|---|
| 表面 | 人物の肖像が描かれている |
| 裏面 | 建物や風景が描かれている |
| 上 | 肖像の頭側が上 |
| 下 | 肖像の足側が下 |
香典袋にお札を入れる時の正しい向き

お札の表裏や上下が分かっても、それを香典袋にどう収めるかで悩む人は多いでしょう。
ここでは「中袋がある場合」と「複数枚のお札を入れる場合」に分けて解説します。
中袋がある場合の入れ方
中袋を使う場合は、お札の表面(肖像側)を下向きにして入れるのが基本です。
つまり、袋の口を上にしたときに、建物や風景の描かれた裏面が見えるようにします。
これは「遺族に直接顔を向けない」という意味が込められており、さりげない配慮の表れです。
複数枚のお札を入れる際の注意点
複数枚のお札を入れるときは、必ず向きをそろえることが大切です。
バラバラに入れると「準備不足」や「雑な扱い」と受け取られかねません。
金額に差があるお札を混ぜても問題はありませんが、できるだけ同じ種類のお札をそろえるとより丁寧な印象になります。
| ケース | 入れ方 |
|---|---|
| 1枚のみ | 表面を下向きにして入れる |
| 複数枚 | すべての向きをそろえて入れる |
| 金額の異なるお札 | 可能なら同じ種類でそろえるのが望ましい |
新札を避ける理由とその背景

お札の入れ方と同じくらい大切なのが、新札を使うかどうかという点です。
実は、葬儀での香典袋に新札は避けるべきとされています。
ここでは、その理由と新札しか手元にないときの対処法を解説します。
なぜ新札は不適切とされるのか
新札を使わない理由は「事前に準備していたように見えるから」です。
まるで不幸が訪れることを予期していたかのように思われ、弔意の気持ちに水を差すことになります。
一方で、お祝いごとのご祝儀袋では新札が「喜びを待っていました」という意味になるため歓迎されます。
この祝いと弔いの真逆の文化を理解しておくことが大切です。
新札しかない場合の対処方法
どうしても新札しか用意できない場合は、軽く折り目をつけてから使用します。
折り目を入れることで、流通したような印象を持たせることができます。
また、金融機関やATMで少し使い込まれた紙幣に両替しておくのも一つの方法です。
| 状況 | 対応方法 |
|---|---|
| 新札が手元にある | 折り目をつけてから使用する |
| 事前に準備できる | 銀行やATMで流通紙幣に両替する |
| 古い紙幣がある | なるべくきれいなものを選ぶ |
中袋がない香典袋の扱い方

地域や宗派によっては、中袋を使わない香典袋が一般的な場合もあります。
その際にも、正しいお札の入れ方や折り方を理解しておくことが重要です。
中袋を使わない地域の習慣
中袋がない理由は「袋を重ねることは不幸が重なるとされる」からです。
特に一部の地域では、この習慣が根付いています。
そのため、中袋がなくても失礼には当たりません。
お札の正しい入れ方と折り方
中袋がない場合は、お札を直接本袋に入れます。
基本は、中袋を使うときと同じく「表面(肖像側)を下向き」にするのがマナーです。
さらに、袋の折り方にも注意しましょう。
下側を先に折り、その上から上側をかぶせることで「悲しみを上から覆う」という意味を持たせます。
| ポイント | 理由 |
|---|---|
| 表面を下向きにする | 遺族に直接顔を向けないため |
| 下から折って上で覆う | 悲しみを静かに包み込む意味 |
| お札の向きをそろえる | 雑な印象を避けるため |
香典袋の封じ方と渡し方のマナー

お札を正しく入れた後は、香典袋の封じ方と渡し方にも注意が必要です。
封じ方ひとつで、相手に与える印象が大きく変わることがあります。
ここでは正しい順序と渡し方のポイントを整理します。
封を閉じる際の順序
香典袋を閉じるときは、下の折りを先に、上の折りを後に重ねるのが基本です。
これは「悲しみを上から覆う」という意味を持ち、弔事特有のマナーです。
逆に上から先に折るのは慶事用であり、香典では使いません。
香典を渡す時の注意点
香典袋は、袱紗(ふくさ)に包んで持参するのが望ましいです。
受付で渡す際は、袱紗から出して相手に向けて差し出します。
このとき、表書きが相手から読める向きになるように注意しましょう。
裸のままバッグから取り出すのはマナー違反とされます。
| 場面 | 正しい対応 |
|---|---|
| 香典袋の折り方 | 下を先に折り、上を後に重ねる |
| 持参方法 | 袱紗に包む |
| 受付での渡し方 | 袱紗から出し、表書きを相手向きにして差し出す |
まとめ:香典袋にお札を入れる際に守るべきこと
ここまで、香典袋にお札を入れる際のルールや注意点を見てきました。
最後に大事なポイントを整理しておきましょう。
お札の向き・新札の有無・袋の扱いの総復習
香典袋にお札を入れるときは、表面(肖像側)を下向きにして、複数枚は必ずそろえるのが基本です。
また、新札は避け、やむを得ない場合は折り目をつけてから使用します。
中袋がない場合も同じルールを守れば安心です。
遺族に敬意を示すための心構え
香典は金額の多さではなく、気持ちの表し方が大切です。
正しいマナーで準備することは、遺族への最大の思いやりとなります。
形式を守りながらも、故人を偲ぶ気持ちを込めることを忘れないようにしましょう。
そうすれば、香典袋を通じてしっかりと哀悼の意を伝えることができます。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| お札の向き | 表面を下向き、裏面を上向きに入れる |
| 新札 | 使用を避ける、やむを得ない場合は折り目をつける |
| 中袋 | ある場合もない場合も同じルールで対応 |
| 渡し方 | 袱紗に包み、受付で丁寧に渡す |